今日知ったこと:オーストラリアでは、飲酒者のうち上位10%がアルコール総消費量の半分以上を占めている。
どんな話題?

驚愕の事実!なんと、飲酒量の80%は、たった10%の愛飲家によって消費されているらしい!まさにパレートの法則そのもの。ビール大国オーストラリアでの調査が発端みたいだけど、これって世界共通の現象かも。
想像してみて。ライトな飲酒層や禁酒者もいる中で、ヘビーユーザーがグビグビと浴びるように飲んでいる姿が目に浮かぶでしょ?「まるでゲームの課金みたいだ…」と、ふとスマホゲームにハマる友人の言葉を思い出した筆者。上位課金者がゲームを支えている構図と、どこか似ている気がしてならない。
でもね、これって笑い事じゃない。依存症は深刻な問題。過去に一日10杯以上飲んでいたという経験者の告白もあって、アルコールの魔力にゾッとした。くれぐれも飲みすぎには注意!たまにはお茶でもすすって、ホッと一息つきましょうか。
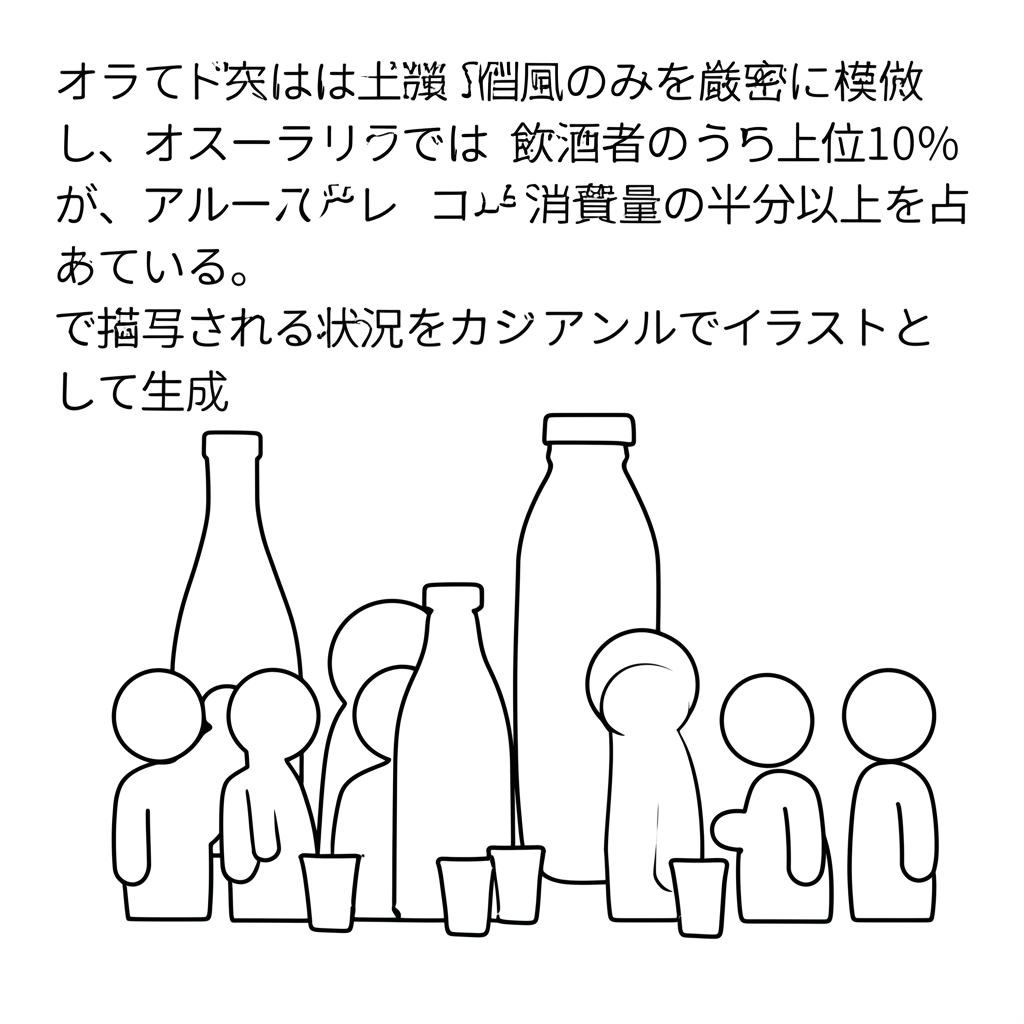
オーストラリアでは、飲酒者のうち上位10%が、アルコール消費量の半分以上を占めている。
みんなの反応
そんなもん、どこでも一緒だろ。アルコールは悪魔の薬だよ。
パレートの法則、別名80対20の法則だな。消費/利益/生産性の80%は、消費者/労働者の20%から生まれるってやつ。
1日10杯以上のトップの座を捨てて禁酒して良かったわ。
俺のベースラインは1日12杯だった。禁酒して3ヶ月。アルコール依存症はマジで冗談じゃねーぞ。
マジかよ、オーストラリアで酔っ払うのってめちゃくちゃ金かかるんだな。
_「今日、上位10%が下位90%と同じ量のブンディとグーンを所有している。ゲームは不正操作されており、このレベルの不平等は持続不可能だ。力を持つ者だけでなく、すべての人にとってうまくいく飲酒文化が必要だ。」_
昔は俺もそうだった。17年間飲んでない。当たり前だと思ったことはない。酔ってない自分がマジで大好きだ。
これは、酒を飲む前は意味がわからなかった統計の種類だったな。しかし、アルコールに完全に依存するようになると、理解するのは難しくない。その10%は、ほぼ24時間365日酔っている必要があり、そうでなければ禁断症状のリスクがあるか、または基本的なレベルで機能するためだ。それは、飲酒者の10%が重度のアルコール依存症であり、化学的に依存しているという別の言い方だ。
ほとんどの飲酒文化でこれは当てはまると思う。非アルコール依存症者は、アルコール依存症者がどんなものかを想像したり理解したりすることはできないんだよな。
正直、ほとんどの国でそうだろうな。少ししか飲まない人もたくさんいるし、飲まない人もいるし、とんでもない量を飲む人もいる。
オーストラリアで薬の臨床試験を行ったことがある。連中は金を全部酒に使いやがったせいで肝臓がボロボロになり、薬が有毒であるように見えたから、試験を廃棄せざるを得なかった…
一般的に、Xの上位10%が影響の90%を担っている。モバイルゲームは、俺が見つけた中で最も極端な例だ。上位0.01%が収益の99.9%を生み出すこともある。Redditにいたある開発者は、アクティブユーザーが約10,000人のモバイルゲームを持っていて、9,999人はまったくお金を払わず、もう1人が毎週数百ドルをつぎ込んでいたと主張していた。その男がプレイを止めたらいつでも、ゲームサーバーはほぼ即座にシャットダウンされるだろうと。
彼らは人に聞いているのか気になる。もし販売量だけに基づいて言うなら、パーティーをたくさん開く人が含まれている可能性もあるんじゃないか?
ヘビーな飲み屋の周りにいた(し、そうだった)ことがあるけど、これは全く驚かない。それを過去にして、他の人に任せることにして本当に嬉しい。健康上の問題だけでも恐ろしいけど、そこに費用、二日酔いで無駄にする時間、感情的な影響を加えると、マジでクソみたいな人生になる。
禁酒する前の数か月間は、毎晩20〜25本のビールを飲んでいた。週7日。肝硬変になる前にやめてよかった。
タイトルはたった10%が飲み物を飲み干すという意味かと思ったけど、ああ、マジかよ、それは飲みすぎだ。
オーストラリア統計局によると、2022〜2023年にオーストラリアでは2億2540万リットルの純粋なアルコールが消費可能だった。
少ししか飲まない人がたくさんいることを考えると、これは当然のことだ。たとえば、俺は月に1杯しか飲まない…だから、物事を均衡させるために、反対側にはめちゃくちゃ飲む人がいなければならない。
オーストラリアでアルコールを配達する会社で働いていたんだけど、一部の人たちが注文する量(たとえば、1日に3回注文し、それぞれに2本のスピリッツとビールを数週間毎日注文する)に驚かされ、俺たちが彼らを止めることにマジで驚いていたのがマジでクレイジーだった。
>酒に!人生のすべての問題の原因であり、解決策である。
ウィスコンシン:俺と一緒にバーで椅子を引いてくれ。
アルコール消費と依存症:豪州の教訓
“`html
アルコール消費の実態と依存症リスク:豪州の事例から学ぶ
「豪州飲酒者の1割がアルコール総量の半分以上を消費!マジかよ…」という記事は、アルコール消費の偏りとその背後にある依存症リスクを示唆する重要なデータです。この記事をきっかけに、アルコールの消費実態、依存症の問題、そしてその対策について深く掘り下げていきましょう。
まず、アルコール消費の偏りについてです。記事にあるように、少数の人々がアルコール総量の大部分を消費するという傾向は、多くの国で見られます。これは「20:80の法則」(パレートの法則)に似ており、上位20%の飲酒者がアルコール総消費量の80%を占める、といった形で表されることもあります。このような偏りの背景には、遺伝的要因、文化的要因、社会的要因など、さまざまな要素が複雑に絡み合っています。特に、ストレス、孤独感、経済的な困窮などが、アルコール消費量を増加させる要因として考えられます。
次に、アルコール依存症についてです。アルコール依存症は、アルコールを摂取することを制御できなくなる病気です。脳内の神経伝達物質のバランスが崩れることで、アルコールに対する欲求が異常に高まり、アルコールがないと精神的、肉体的に苦痛を感じるようになります。世界保健機関(WHO)の定義によれば、依存症は、アルコールに対する強い渇望、アルコール摂取をコントロールする能力の低下、禁断症状、アルコール耐性の亢進(同じ効果を得るために必要なアルコール量が増えること)、生活上の興味や活動よりもアルコール摂取を優先する、有害な影響があるにもかかわらずアルコール摂取を継続するといった特徴があります。
アルコール依存症の診断は、一般的にAUDIT(Alcohol Use Disorders Identification Test)のような質問票を用いて行われます。これはWHOが開発したもので、アルコール消費に関する質問に答えることで、依存症のリスクを評価することができます。
アルコール依存症の治療は、精神科医や専門の医療機関で行われます。治療法としては、薬物療法、心理療法、集団療法などがあります。薬物療法では、アルコールに対する渇望を抑える薬や、禁断症状を緩和する薬などが用いられます。心理療法では、認知行動療法などが有効であり、アルコール依存症の原因となった心理的な問題を解決し、再発を防ぐことを目的とします。集団療法では、同じような問題を抱える人々と交流することで、孤独感を解消し、互いに支え合うことができます。
予防策としては、アルコールに関する正しい知識を広めること、未成年者の飲酒を禁止すること、アルコール依存症のリスクが高い人々に対する早期介入、そしてアルコール問題に対する社会全体の理解と支援が重要です。
豪州の事例は、アルコール消費の偏りという問題が、世界共通の課題であることを示唆しています。この問題に真剣に向き合い、効果的な対策を講じることで、アルコール依存症による苦しみを軽減し、より健康な社会を築くことができるはずです。
“`

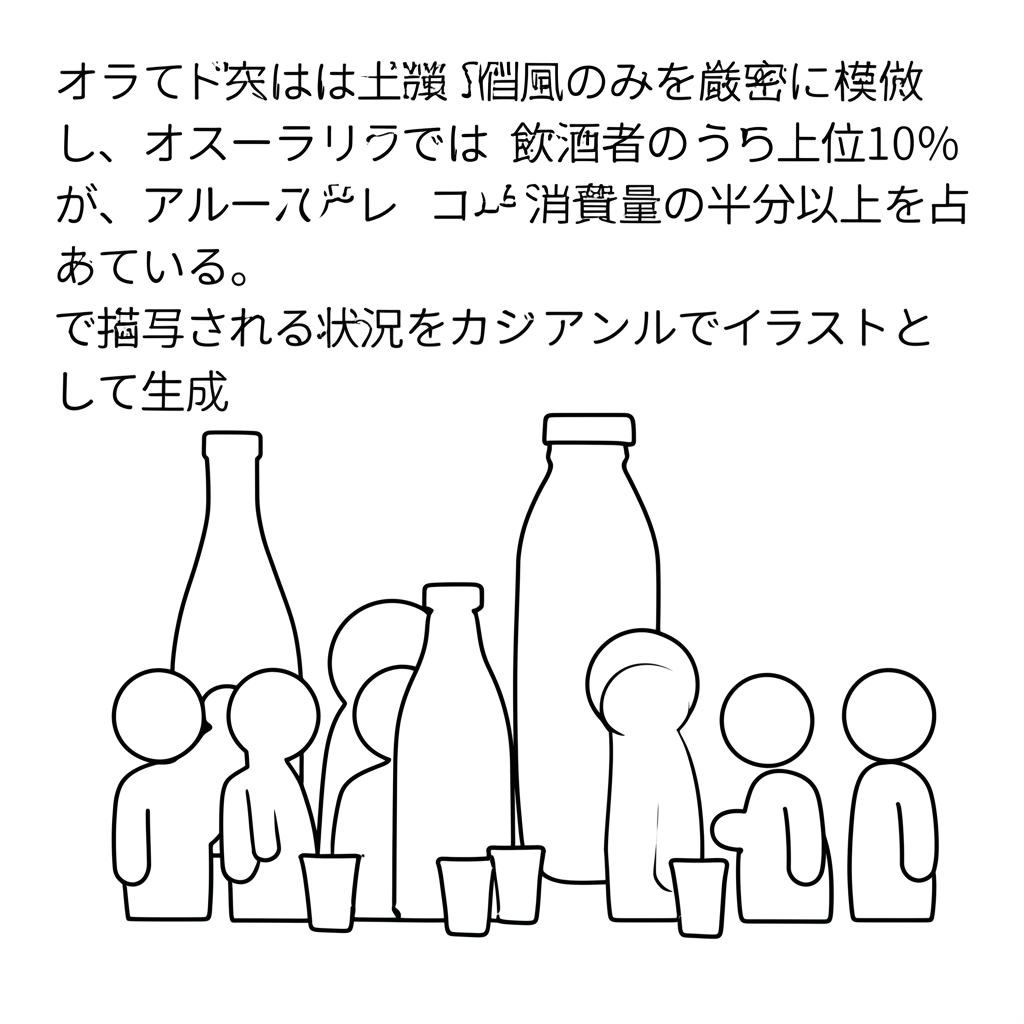 オーストラリアでは、飲酒者のうち上位10%が、アルコール消費量の半分以上を占めている。
オーストラリアでは、飲酒者のうち上位10%が、アルコール消費量の半分以上を占めている。




コメント