どんな話題?

「< b >Malört」という謎の酒、ご存知ですか?シカゴ名物(?)らしいのですが、その味は一筋縄ではいかない様子。「苦い革靴」「鉛筆の削りかすと駅の小便」「汗臭い靴下を焼いた味」など、散々な言われよう!しかし、飲んだ直後は意外と平気で、後から地獄がやってくるという声も。まるで< b >ジェットコースターのような味わいでしょうか。
調べてみると、スウェーデン由来の「< b >Bäsk(ベスク)」という薬草酒の一種らしい。シカゴに渡った移民が広めたとか。中には「好きだ!」という強者も存在し、周囲が驚いておごってくれるという、ちょっとお得な体験もできるみたい。まるで罰ゲームドリンク?
先日、近所の飲み屋で「謎の薬草酒、あります」という手書きのPOPを発見。もしかして、Malört!?恐る恐る注文してみると、想像を絶する苦味に顔がグシャッ。でも、どこか懐かしいような…そうだ、< b >子供の頃に飲んだ苦い漢方薬にそっくりだ!罰ゲームではなく、これはもしかして…< b >健康ドリンク?
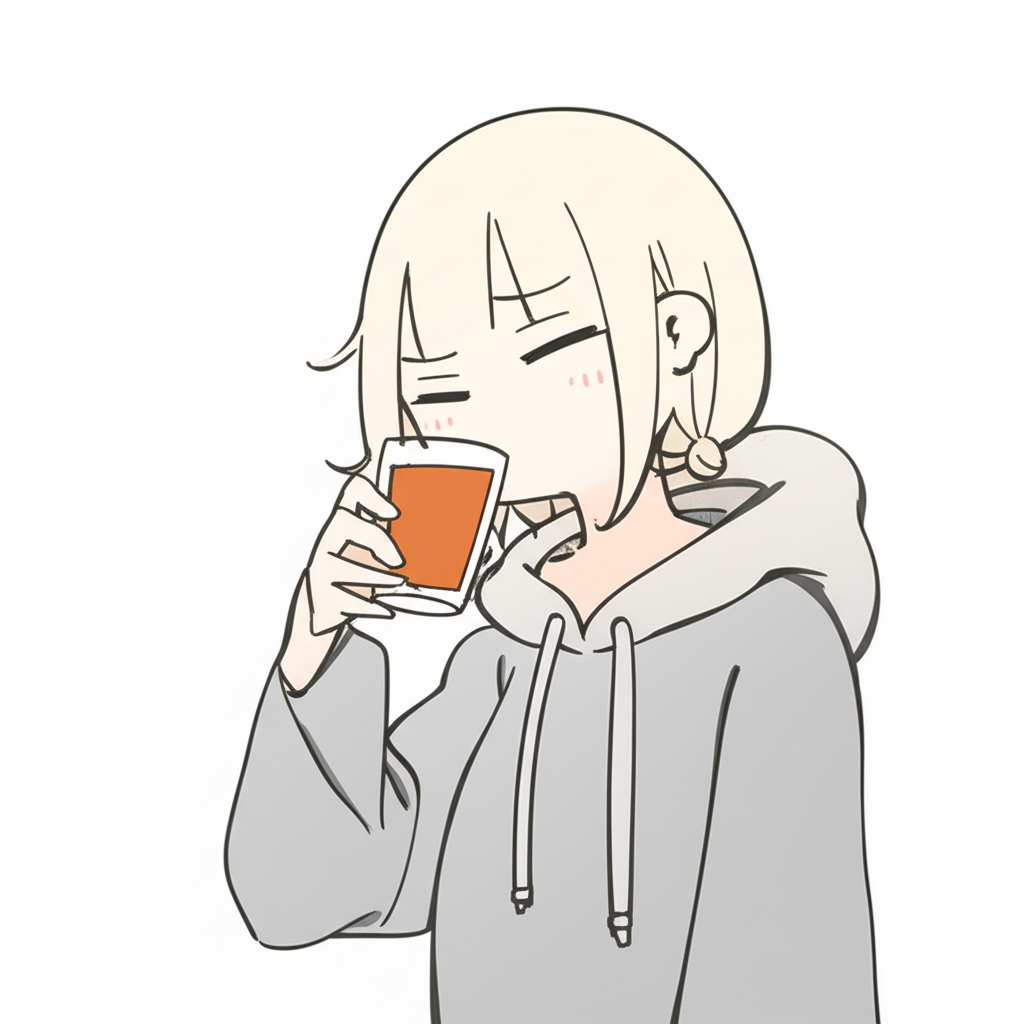 シカゴ限定の強いリキュール、マローツは「ガソリン入りの焦げたコンドームを飲み込むよう」と評される。ショットを飲むことはシカゴの通過儀礼とされている。
シカゴ限定の強いリキュール、マローツは「ガソリン入りの焦げたコンドームを飲み込むよう」と評される。ショットを飲むことはシカゴの通過儀礼とされている。
みんなの反応
シカゴ名物マロート:ゲロマズ酒の魅力
“`htmlシカゴ名物として知られる**Malort(マロート)**は、その独特すぎる**taste(味)**で、一度飲んだら忘れられない、あるいは二度と飲みたくないとまで言われる**liquor(リキュール)**です。インターネット上では「ゲロマズすぎてワロタ」などと揶揄されることもありますが、地元シカゴの人々にとっては単なる酒以上の存在、一種の通過儀礼のような位置づけとなっています。
**マロート**の主原料は、**ニガヨモギ**というキク科の植物です。ニガヨモギは、英語ではwormwoodと呼ばれ、アブサン(absinthe)という強いアルコール度数のリキュールにも使われています。アブサンも独特の苦味がありますが、**マロート**はそれをさらに強烈にしたような**taste**が特徴です。苦味に加え、薬品のような香り、土のような風味、そして後から来る強烈な渋みが組み合わさり、形容するのが難しい複雑な**taste**を作り出しています。
ではなぜ、こんなに強烈な**taste**の**liquor**がシカゴで愛されているのでしょうか?その理由はいくつか考えられます。まず、シカゴの歴史的な背景です。19世紀後半から20世紀初頭にかけて、シカゴには多くの移民が流入しました。彼らは故郷の薬草や香草を使った**liquor**を好んで飲んでおり、**マロート**もそうした伝統を受け継いだものと考えられます。また、禁酒法時代に密造酒として製造・流通していたことが、その希少価値を高め、地元民の愛着を深めたという説もあります。
統計データとしては、**マロート**の正確な販売量は公開されていませんが、シカゴ周辺のバーや酒店では必ずと言っていいほど取り扱われています。観光客向けの面白グッズとしての需要も高く、地元の土産物店でも人気があります。インターネットでのレビューやSNSでの反応を分析すると、初体験者の多くは「まずい」「ありえない」といった否定的な意見を述べる一方、地元民や**マロート**愛好家は「クセになる」「独特のうまさがある」と肯定的な意見を述べています。この対照的な反応が、**マロート**のユニークさを物語っていると言えるでしょう。
心理学的な側面から見ると、**マロート**を飲む行為は、一種の挑戦、あるいは集団への帰属意識を示す行為と解釈できます。強烈な**taste**に耐え、それを乗り越えることで、仲間意識が芽生え、シカゴの一員としてのアイデンティティを確立するというわけです。地元民が**マロート**を「通過儀礼」と呼ぶのは、まさにこの心理的な効果を反映していると言えるでしょう。
結論として、**Malort**は単なる**liquor**ではなく、シカゴの歴史、文化、そして人々のアイデンティティが凝縮された存在です。その強烈な**taste**は、多くの人にとっては苦痛かもしれませんが、一部の人にとっては忘れられない思い出となり、シカゴという街を象徴する味わいとして、これからも受け継がれていくでしょう。機会があれば、ぜひ一度、**マロート**に挑戦してみてはいかがでしょうか?ただし、覚悟は必要です!
“`



コメント