航空母艦の顕著なカーブ(反り返り)はなぜあって、そしてなぜ転覆しないのか?
どんな話題?

[要点生成失敗]
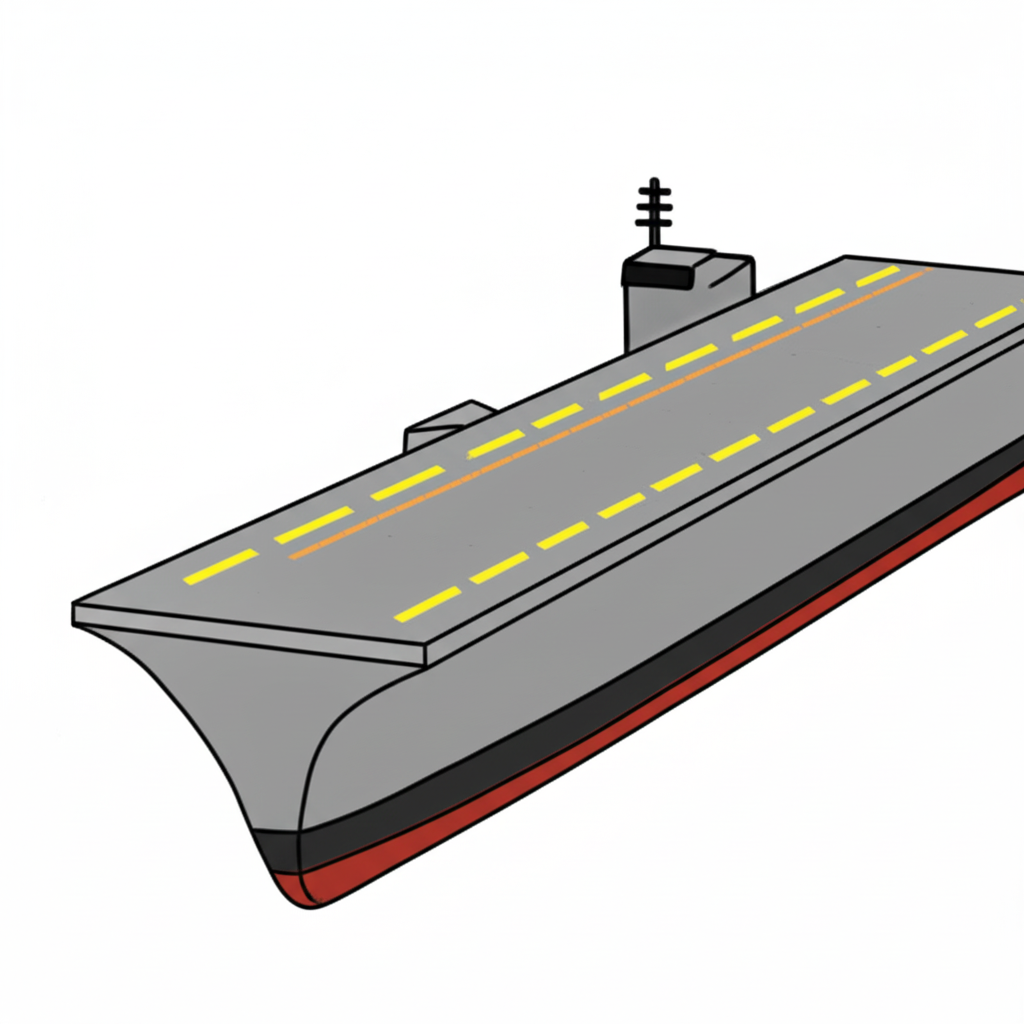
空母の異様なカーブ(反り返り)は、航空機の運用効率を高めるための設計。重心バランスを保ち転覆を防ぐ構造になっている。
みんなの反応
重い部品は下の方に、浮力を生み出すための幅広で安定した船体、そして重量を調整して傾きを打ち消すためのアクティブバラストシステム。浮力の上向きの力と重力の引っ張りのバランスが重要なんだよね。底の重りが常に沈めようとするけど、上半分は浮力が強すぎて沈まないから、上部が垂直に水面に浮かぶことになる。水中の重りが重すぎてて、テコの原理で転覆できないんだよ。
理由はこれだよ、キールが見えてないだけ。それがバラストなんだわ。
お前さんは、船が水面下にあんまりないって勘違いしてんだよ。写真じゃ見えない部分が結構あるんだわ。
その硬さが、曲面にもかかわらずソレを直立させているんだ。
そのおかげで、コーナーをよりうまくドリフトできるんだぜ。
ここで見てるカーブは、船首部分だけで、水切りを良くして抵抗を減らすためなんだわ。
要するに数学。物理学って呼ぶけど、結局は数学だ。クレイジーな数学だよ。
意図的に安定のために底に重量を追加してるの?もしそうなら、重量が増えるのはマイナスだから、もっと良い設計はないのか?
細い部分の下は広くて楕円形なんだ。オンラインで船を調べてみろ。転覆しないように重量と浮力の比率が計算されてるんだよ。
質問。最初の写真で、どうやってあんなに近づくことが許されたんだ? 問題の船は解体業者にあるのか? 俺が乗ってた船に近づこうとするやつは、予告なしに110ヤード以内で吹き飛ばされてたぞ。
もし逆だったらどうなるか考えてみろ、ただの筒みたいなもんだ。ずっと傾いたり転がったりし続けるだろ。
手前にあるハードチャインのカヤックの方がよっぽど面白いな。あのロッカーを見てみろ! あれは「遊び心のある」ボートだ。疲れ果てずにそれを真っ直ぐ進めるには、かなりのスキルが必要だぞ。
非常に厳格な海洋工学の基準に従って建設されてるんだよ。段ボールも、段ボールの派生物も、紙も、紐も、セロテープも使わない。
レンズと遠近法によって、実際よりもずっと細く見えるんだ。もっと良い写真があるぞ。それに、上にあるものは、下にあるバラスト、機器、原子炉、エンジン、物資などに比べて、非常に軽いんだ。飛行甲板の下にある格納庫デッキは、ほとんど空っぽの空間だよ。
水面下には重いもの。上には巨大な「空っぽ」(つまり非常に浮力がある)空間。
バカな質問かもしれないけど、飛行甲板の下や船体の下部に、接近する物体を見るためのカメラが設置されてるの?
おっぱい! 女性がチップを払わないのと同じ理由だ! これって常識だと思ってたんだけど!
空母に駐留してた海軍のベテランとして、みんなのコメントに笑わせてもらったわ😂
空母が傾かない秘密:浮力と重心の妙技
以下に、キーワード「**船舶安定性**」、「**浮力**」、「**重心**」をテーマにした解説を、記事「空母の異様なカーブ、アレ傾かない理由ワロタwww」を背景に、独自の視点と背景情報を加えて作成します。
**船舶安定性:なぜ巨大な空母は転覆しないのか?**
「空母の異様なカーブ、アレ傾かない理由ワロタwww」という記事は、空母という巨大な船が、なぜ激しい波の中でも転覆することなく安定していられるのかという疑問をユーモラスに提起しています。この疑問を理解する鍵は、**船舶安定性**という概念、そしてそれを支える**浮力**と**重心**という2つの重要な要素です。
**浮力:水を押しのける力**
**浮力**とは、水中に物体を置いた時に、物体を押し上げる力のことです。アルキメデスの原理によると、物体が押しのけた水の重さと等しい力が**浮力**として働きます。船は、その船体によって押しのけた水の重さが、船自体の重さと等しくなるように設計されています。つまり、船の重さと**浮力**が釣り合っている状態なので、船は水に浮かぶのです。空母のような巨大な船は、莫大な量の水を押し退けることで、自身の巨大な重量を支えるだけの**浮力**を得ています。船体の大きさや形状は、この**浮力**を最大限に活かすように計算されています。
**重心とメタセンター:安定性の要**
船が安定しているかどうかは、**重心**の位置と**メタセンター**という仮想点の関係で決まります。**重心**は、船全体の重量が集中している点です。一方、**メタセンター**は、船がわずかに傾いた時に、**浮力**の中心が移動する軌跡が作る交点です。**メタセンター**が**重心**よりも上に位置していれば、船は傾きから回復しようとする力(復原力)が働き、安定を保ちます。逆に、**メタセンター**が**重心**よりも下にあると、船は傾きを増幅させてしまい、転覆の危険性が高まります。
**空母の異様なカーブ:傾斜を制御する秘密**
記事で触れられている空母の「異様なカーブ」は、船の幅を広くし、喫水線付近の形状を工夫することで、**メタセンター**の位置を高く保ち、安定性を高めるための設計です。幅が広いほど、船が傾いた時の**浮力**の中心の移動距離が大きくなり、**メタセンター**の位置が上昇します。また、喫水線付近の形状を工夫することで、傾いた際に水に浸かる部分の体積変化を大きくし、より大きな復原力を生み出すことができます。
**バラストとヒーリングシステム:能動的な安定化**
空母のような大型艦艇は、**重心**の位置を調整するために、バラスト(重り)を積んだり、ヒーリングシステムと呼ばれる注排水システムを用いて、左右のタンクに水を移動させることで**重心**を移動させたりします。特に、航空機の発着艦時には、航空機の移動に伴い**重心**が大きく変動するため、ヒーリングシステムによる能動的な制御が不可欠です。これにより、船体の傾きを最小限に抑え、安定した運用を可能にしています。
**まとめ:技術の粋を集めた船舶安定**
**船舶安定性**は、**浮力**と**重心**という基本的な物理原理に基づいていますが、それを実現するためには高度な設計技術と運用技術が必要です。空母の「異様なカーブ」やバラスト、ヒーリングシステムなどは、その具体的な現れと言えるでしょう。一見ユーモラスに見える疑問も、掘り下げていくことで、高度な技術と緻密な計算に支えられた、人類の知恵の結晶であることがわかります。

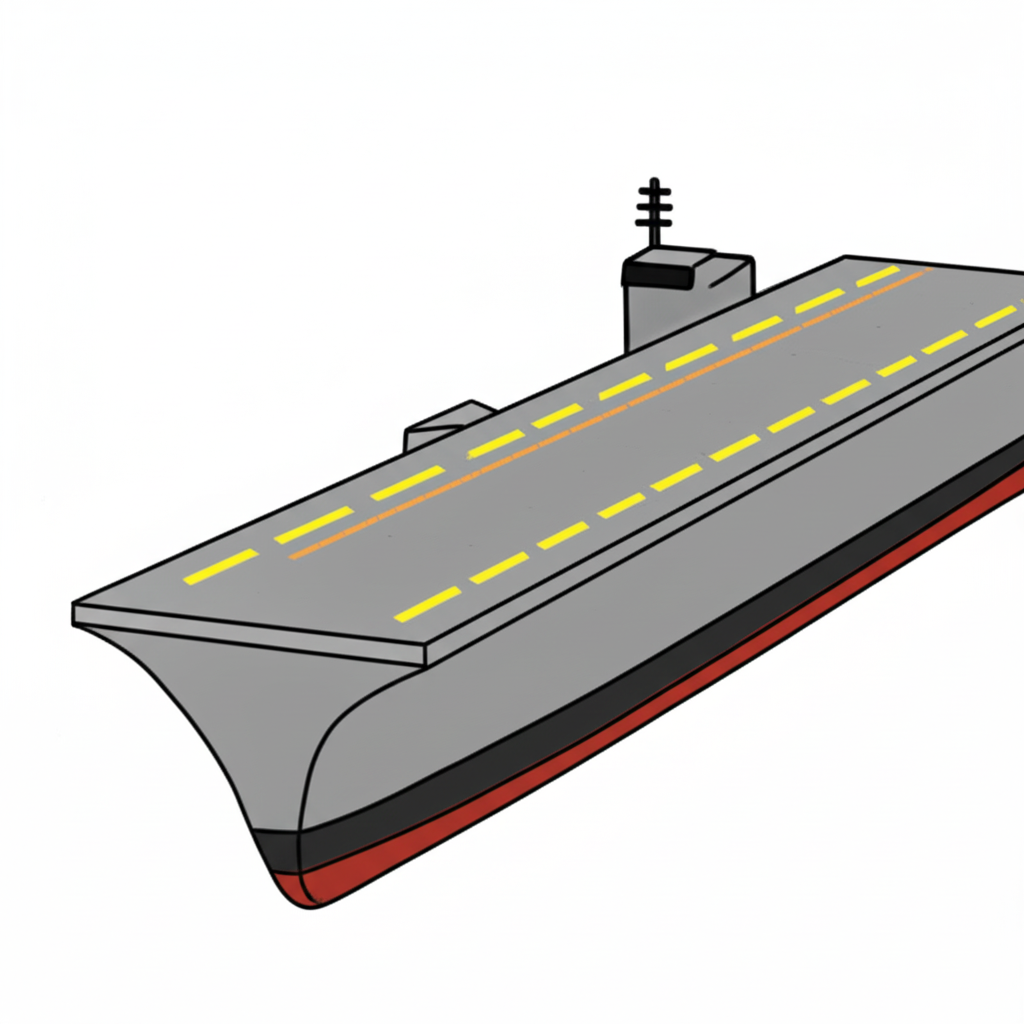 空母の異様なカーブ(反り返り)は、航空機の運用効率を高めるための設計。重心バランスを保ち転覆を防ぐ構造になっている。
空母の異様なカーブ(反り返り)は、航空機の運用効率を高めるための設計。重心バランスを保ち転覆を防ぐ構造になっている。




コメント