今日知ったこと:虚栄のサイズ表示について。アパレル企業は、実際よりも小さく服のサイズを表示するのが常套手段らしい。表示されているウエストサイズが34インチでも、メーカーによっては最大6インチも異なることがある。企業間で一貫した基準はない。
どんな話題?

ファッション界のサイズ表記は、もはや当てにならない件について。多くの人が経験しているように、同じブランド、同じサイズ表記でも、実際に着てみると全く違うという現象が頻発しています。まるでブランド同士が密かに結託して、消費者を混乱させているかのよう。
特に女性服のサイズ表記は「気まぐれ」そのもの。ある店では2、別の店では6…もはやロシアンルーレット状態です。男性服も例外ではなく、インチ表記ですらアテにならない始末。
この矛盾の根源には、「虚栄サイズ」というマーケティング戦略があるようです。つまり、消費者を「痩せている」と錯覚させ、購買意欲を刺激するわけですね。
先日、古着屋でジーンズを買ったのですが、店員のおばちゃんが「あら~、最近の若い子は足が長いねぇ!」と、ニヤニヤしながら裾上げをしてくれました。…いや、それただ単に、昔のサイズ表記がテキトーだっただけでは?と心の中でツッコんだのは、内緒です。結局、そのジーンズ、家で履いてみたら、ブカブカだったんですよね…とほほ。
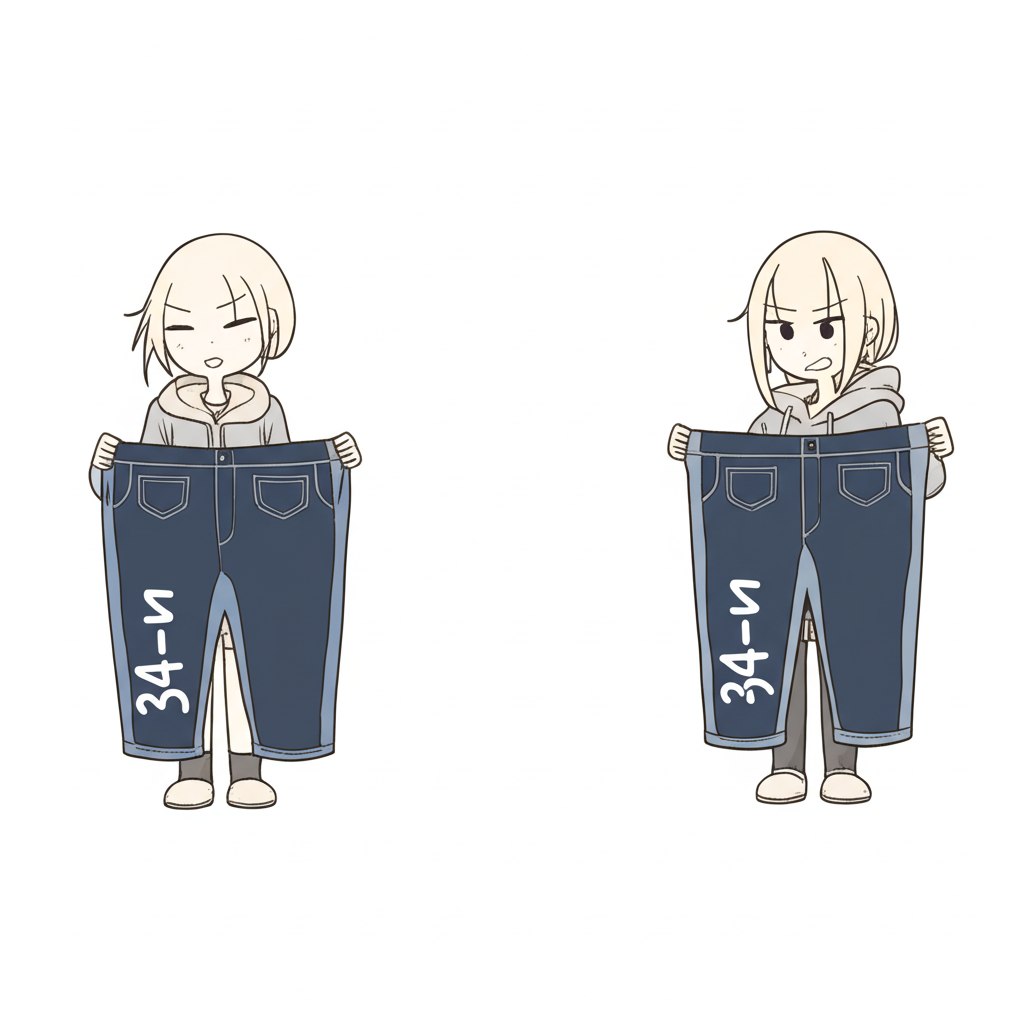
洋服のサイズ表記は実際より小さく表示される「虚栄のサイズ設定」がある。同じ34インチ表記でも、メーカーによって6インチも差が出ることがあり、統一された基準はない。
みんなの反応
EUのいいところは、消費者保護法がガチガチなとこだな。S/M/L/XLとかアホなタグじゃなくて、ちゃんとcmで表示しろってうるさい。
ワイも今日r/comicsのトップ読んだわ。[まさに**バニティサイジング**についての漫画で、この投稿の1時間前に投稿されたやつ。](https://www.reddit.com/r/comics/comments/1n0lx18/jeans/)
ランダムなノーブランドの服の方がフィット感が良い理由がやっとわかったわ。あれって、書いてあるサイズがマジなんだな。
それは男だからだろ。女は昔から文句言ってんだよ。店によって2だったり6だったりするんだぞ。男のパンツみたいに、ちゃんと寸法で表示しろっつーの。
もう昔からずっと問題になってる。一番ムカついたのは、店でリーバイス買ったらあるサイズがピッタリで、ちょっと余裕もあるくらいだったのに、同じリーバイスの別のSKUをオンラインで6本注文したら、**マジでキツすぎて履けなかった**こと。
サイズ34って書いてあっても、それが34インチとは限らないんだよ。メーカーが勝手に決められるんだから。もちろん、インチって書いてあれば別だけどな。
マジレスすると、お前人生で一回でも服買ったことある?
靴も同じ。大きめのサイズ番号をつけて、自社ブランドの靴を買わせるんだよな。言ってるの**お前のことだぞ、NIKE**。
身長188cmの俺だけど、Lサイズって書いてあるのに実際はMサイズみたいな服によく遭遇する。34×34のパンツが実際は32×34だったりとか。
インチでサイズ表記してあるなら、インチは統一規格なんだから、そういうことにはならないはずだと思うじゃん?
私はいつもヒップサイズで選んでる。絶対に一番大きいとこで合わせる。女性の場合、ウエストはヒップより小さいから。
逆のパターンもあるんだよな。10〜20年前に買ったターゲットとかの服。Lサイズがちょうどよくて、ゆったり着れてた。でも、まったく同じスタイルの新しいLサイズは、キツくて、丈が短くて、胸周りがめっちゃ狭い。XLでも昔のLサイズよりキツいんだよ。いろんなブランドで同じような経験してるわ。
サイズの誤差が一番最悪。もうワークパンツはオンラインで買わない。同じ36×34のパンツを3本注文したのに、同じ色で同じメーカーなのに、1本はウエストが**デカすぎ**、1本は**小さすぎ**、1本は**丈が短すぎ**だった。
20年くらい前にバナナリパブリックのアウトレットで働いてたけど、アウトレットモールって本来は売れ残りとか不良品を送る場所のはずなのに、「メインストアのバナナリパブリックを買うほど金がない人向け(だけどお金は持ってる)」って扱いだったんだよね。ちょっと質を落とした別の服を作ってて、バニティサイジングは当たり前だし、特定の体型を想定してるのがバレバレだった。GAP Inc全体のビジネスモデルがそんな感じだった。痩せてて曲線がない人はBR。ちょっと太ってる人はGAP。貧乏なデブはOld Navyで買え、みたいな。マジでクソだった。もう何年もBRに行ってないけど、変わってないと思う。
これマジでクソ。昔はメンズの服はもっとサイズが統一されてた。首回りのサイズが16.5インチから18インチまでバラバラなのに、全部着れるドレスシャツがある。この範囲の中間のサイズを買ったら、**まるでギロチン**みたいなのもある。俺の経験では、ラルフローレンが一番サイズの一貫性がない。
Dickiesはマジメなブランドだと思う。他のブランドで快適なサイズでDickiesのパンツとかショーツを買うと、キツいんだよな。それが正確なサイズなんだろうな、って思ってる。
靴にも当てはまる。あるブランドではこのサイズなのに、別のブランドではハーフサイズ大きい/小さいサイズを履く人がいるのは、そういうこと。
マリリン・モンローはサイズ16だったけど、今だとサイズ6(か、もっと小さいサイズ)になるって言うと、みんな黙り込むんだよな。去年、Poshmarkでパンツを買ったんだけど、8/9って書いてあって、いつも履いてるサイズだったのに、**4インチもデカかった**。あと、ポケットな。
服のサイズ表記問題:消費者保護の視点から
“`html
【衝撃】服のサイズ表記の不整合問題:消費者保護の視点から徹底解説
近年、オンラインショッピングの普及に伴い、衣服のサイズ表記の不整合に関する問題が深刻化しています。特に、記事「【衝撃】服のサイズ表記ガバガバすぎ!34インチが最大6インチも違うとかマジ?」で指摘されているように、同じサイズ表記であっても、ブランドや商品によって実際の寸法が大きく異なるケースが頻発しており、消費者の混乱を招いています。本稿では、この問題の現状を分析し、統計データに基づいてその深刻さを解説するとともに、消費者保護の観点から、その解決策を探ります。
サイズ表記の不整合は、消費者に様々な不利益をもたらします。例えば、オンラインで購入した服が実際に着用してみるとサイズが合わず、返品・交換の手間が発生したり、場合によっては送料などの追加費用が発生したりします。また、サイズが合わない服を着ることで、体型へのコンプレックスを感じたり、精神的なストレスを感じたりする人もいます。
この問題を裏付ける統計データとして、独立行政法人国民生活センターに寄せられる衣料品のサイズに関する相談件数があります。具体的な数値は年度によって変動しますが、毎年一定数の相談が寄せられており、その内容は「サイズ表記と実際の寸法が異なる」「同じブランドでも商品によってサイズ感が違う」といったものが多く見られます。また、ECサイトのレビュー欄などでも、サイズに関する不満の声が散見されます。
サイズ表記の不整合が発生する原因はいくつか考えられます。まず、各ブランドが独自のサイズ基準を採用していることが挙げられます。これは、各ブランドがターゲットとする顧客層やデザインによって、最適なサイズ感が異なるため、一概に統一された基準を設けることが難しいという側面もあります。しかし、その結果、消費者はブランドごとにサイズを覚え直す必要が生じ、購入時の混乱を招いています。
また、縫製技術や素材の違いもサイズ感に影響を与えます。同じサイズ表記であっても、伸縮性の高い素材を使用している場合と、そうでない場合とでは、着用感が大きく異なります。さらに、海外ブランドの場合、日本と欧米では体型が異なるため、同じサイズ表記でも寸法が異なることがあります。
このような状況を踏まえ、消費者保護の観点から、以下の対策が求められます。
1. サイズ表記の標準化:業界全体で統一されたサイズ基準を設けることが理想的です。少なくとも、各ブランドは自社のサイズ基準を明確に公開し、消費者が容易に確認できるようにする必要があります。
2. 寸法情報の詳細な提供:商品の詳細情報として、着丈、身幅、袖丈などの寸法を明記することで、消費者はより正確なサイズ判断が可能になります。特に、オンラインショップでは、モデルの身長や着用サイズを記載するだけでなく、複数方向からの写真や動画などを掲載することで、消費者の不安を軽減することができます。
3. 試着環境の整備:実店舗では、十分な試着スペースを確保し、消費者が実際に商品を試着できるようにする必要があります。オンラインショップでは、バーチャル試着や、AR技術を活用した試着体験を提供することで、消費者の購買意欲を高めることができます。
4. 消費者教育の推進:消費者自身が、自分の体型を正確に把握し、ブランドごとのサイズ基準を理解することが重要です。そのため、消費者庁や国民生活センターなどの機関が、サイズに関する情報提供や啓発活動を積極的に行う必要があります。
衣服のサイズ表記の不整合問題は、消費者の利便性を損なうだけでなく、経済的な損失や精神的なストレスを引き起こす可能性のある深刻な問題です。上記のような対策を講じることで、消費者が安心して服を購入できる環境を整備し、より良い消費者体験を提供することが求められます。
“`

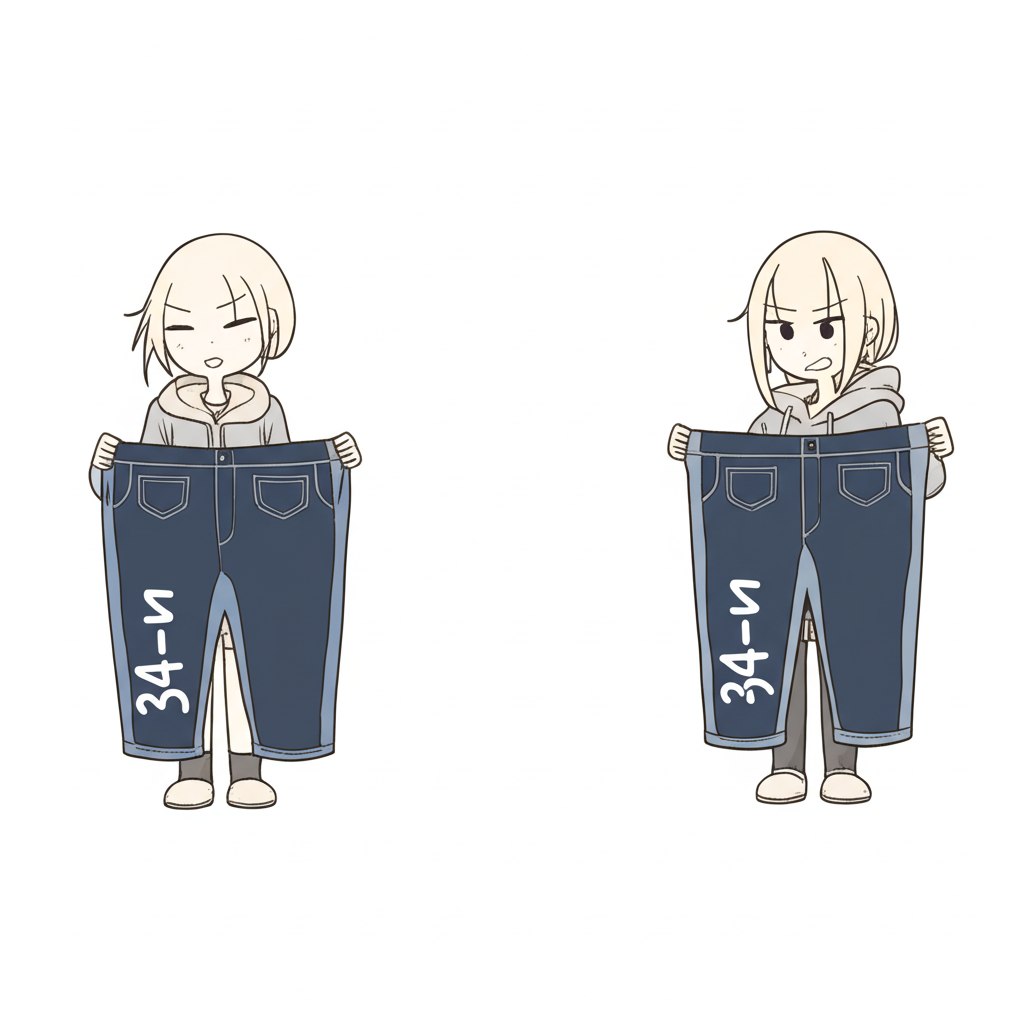 洋服のサイズ表記は実際より小さく表示される「虚栄のサイズ設定」がある。同じ34インチ表記でも、メーカーによって6インチも差が出ることがあり、統一された基準はない。
洋服のサイズ表記は実際より小さく表示される「虚栄のサイズ設定」がある。同じ34インチ表記でも、メーカーによって6インチも差が出ることがあり、統一された基準はない。




コメント