どんな話題?

衝撃の事実!親は子どもを平等に愛しているとは限らない?ある調査によると、親の約7割が子どもを区別している可能性があるというのです。長子や末っ子、同性の子供が可愛がられやすい傾向にあるとか。中には、兄弟姉妹に家をプレゼントする親も…。
この話題に、ネット上では阿鼻叫喚。「やっぱりね…」という諦め顔や、「うちの子は二人とも可愛い!」という親御さんの声も。オノマトペで表現するなら「うちの子ラブ度は、ドッコイドッコイ!」って感じでしょうか。でも、ちょっと待ってください。愛情の形は千差万別。親だって人間だもの、フィーリングが合う合わないはあるでしょう。
個人的な見解ですが、親の愛情表現が不器用なだけかもしれません。「うちの親は絶対、兄貴贔屓だ!」と嘆く友人も、実は兄貴が苦労している時にだけ親から連絡が来ることを知って、ちょっと複雑な気持ちになったとか。愛情の裏返しってやつですかね?いずれにせよ、愛されているかどうかの判断は、子どもの主観的なものなのかもしれませんね。愛されたい気持ちが先行すると、どうしても親の些細な言動が気になってしまうもの。難しい問題です。
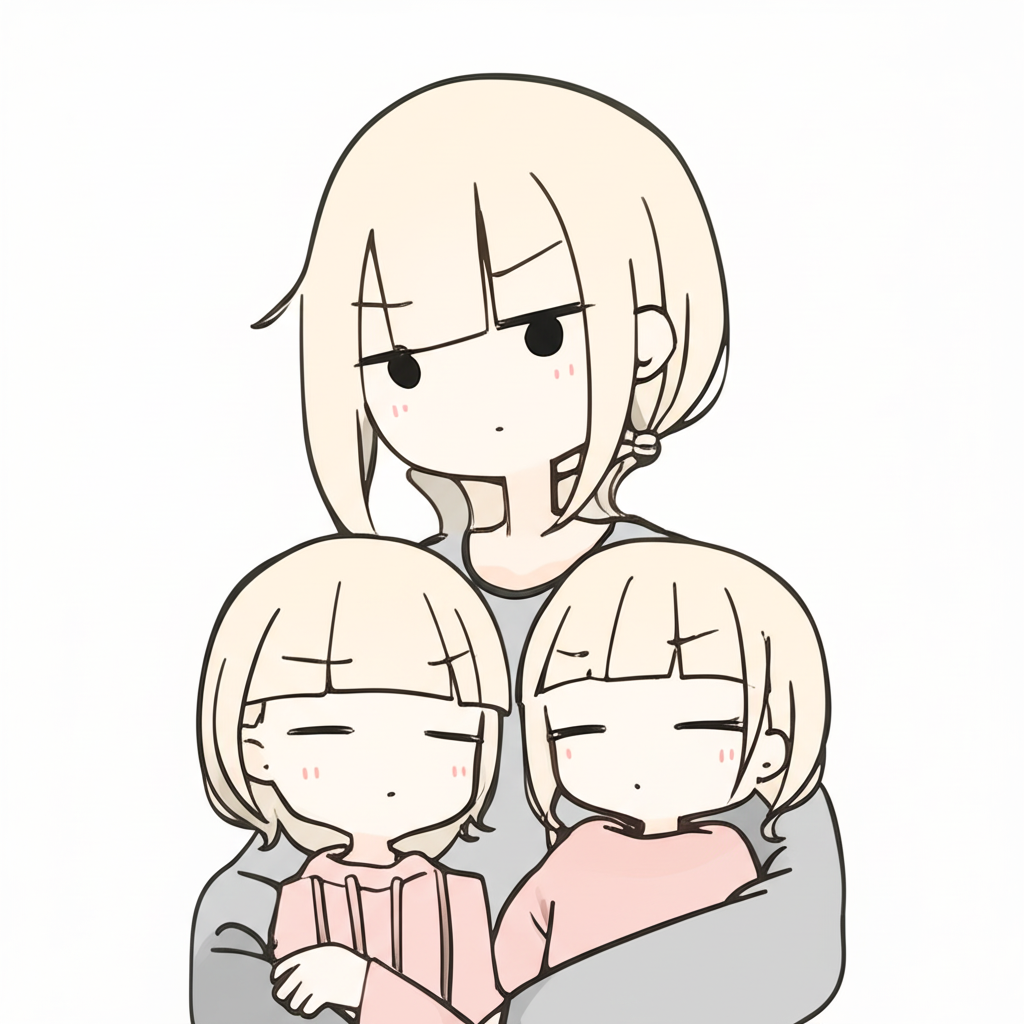 研究によると、複数の子供を持つ親の約70~74%は、お気に入りの子供がいることが示されています。
研究によると、複数の子供を持つ親の約70~74%は、お気に入りの子供がいることが示されています。
みんなの反応
親のえこひいき:影響と対策
“`html兄弟姉妹がいる家庭において、親の**favoritism(えこひいき)**は、深刻な問題としてしばしば取り上げられます。記事「7割超の親に favoritism発覚!兄弟格差の実態ワロタ」が示すように、多くの親が意図的、あるいは無意識的に、子供たちへの対応に差をつけている可能性があることが示唆されています。今回は、このテーマについて、分析や統計を交えながら、より深く掘り下げて解説します。
まず、**favoritism**がなぜ起こるのかを考えてみましょう。親が特定の子供をひいきしてしまう背景には、様々な要因が考えられます。例えば、子供の性格や特性が親自身の価値観と合致している場合、親はより親近感を覚えやすくなります。また、生まれた順番によって、親の期待や接し方が変わることもあります。第一子には過剰な期待をかけたり、末っ子を甘やかしてしまうといったケースが一般的です。さらに、子供の性別、外見、才能などが、親の愛情表現に影響を与える可能性も否定できません。
具体的な**統計**を見てみましょう。心理学の研究によれば、親の**favoritism**を自覚している子供は、そうでない子供に比べて、自尊心が低くなる傾向があることが示されています。また、兄弟姉妹間の関係が悪化しやすく、嫉妬心や競争意識が強まることも報告されています。興味深いのは、ひいきされる側の子どもも、罪悪感やプレッシャーを感じることがあるということです。特に、周囲から「親のお気に入り」と見なされることで、孤立感や疎外感を抱くケースも少なくありません。
記事タイトルにある「7割超の親に **favoritism** 発覚」という数字は衝撃的ですが、この数字が示すのは、必ずしも親が悪意を持って差別しているということではありません。多くの場合、親は公平であろうと努めていますが、無意識のうちに、あるいは状況に応じて、対応に差が出てしまうことがあります。例えば、病弱な子供や困難を抱えている子供に対して、より多くの時間や注意を割くことは、必ずしも**favoritism**とは言えません。大切なのは、子供たちがその理由を理解し、親の愛情を感じられているかどうかです。
では、親はどのように**favoritism**を防ぐことができるのでしょうか。最も重要なのは、まず、自身が子供たちへの接し方に偏りがないかを意識することです。子供一人ひとりの個性やニーズを理解し、それぞれの成長段階に合わせた愛情表現を心がけましょう。また、兄弟姉妹間の競争心を煽るような言動は避け、お互いを尊重し、協力し合うように促すことが大切です。例えば、「〇〇はお兄ちゃんだから我慢しなさい」といった言葉は、特定の子に負担を強いることになるため、避けるべきです。代わりに、「〇〇も頑張っているね」「〇〇のこういうところが素晴らしいね」といった具体的な言葉で、それぞれの良い点を認め、褒めるようにしましょう。
最後に、**favoritism**は、家庭環境だけでなく、子供たちの将来にも影響を与える可能性があります。幼少期に受けた心の傷は、大人になってからも人間関係や自己肯定感に影響を及ぼすことがあります。親は、子供たちが安心して成長できる環境を整えるために、**favoritism**の問題に真摯に向き合い、改善していく努力が必要です。専門家のカウンセリングを受けることも有効な手段の一つです。
この記事が、**favoritism**の問題に対する理解を深め、より良い親子関係を築くための一助となれば幸いです。
“`



コメント