Ever wondered how these giant wind turbines are installed?
byu/gabito705 ininterestingasfuck
どんな話題?

“`html
風力発電機の建設風景に、世界が「ワオ!」
この記事では、巨大な風力発電機が、まるで精密機械のように組み立てられていく様子を解説しています。
建設現場は、強風吹き荒れる高所。そこで働く人々は、巨大な油圧レンチを駆使し、巨大なボルトを締め上げていきます。その光景は、まるで巨大なプラモデルを組み立てるかのよう。
驚くべきは、そのスピード。あっという間に巨大な風車が組み上がっていく様子は圧巻です。
実は、90年代の紛争地域で、自家製の風力発電機を多数見かけたことがあります。廃品利用のモーターとバッテリーを組み合わせた、言わば“DIY風車”。荒れた土地でも、創意工夫でエネルギーを生み出そうとする人々の姿に、心を打たれました。
“`
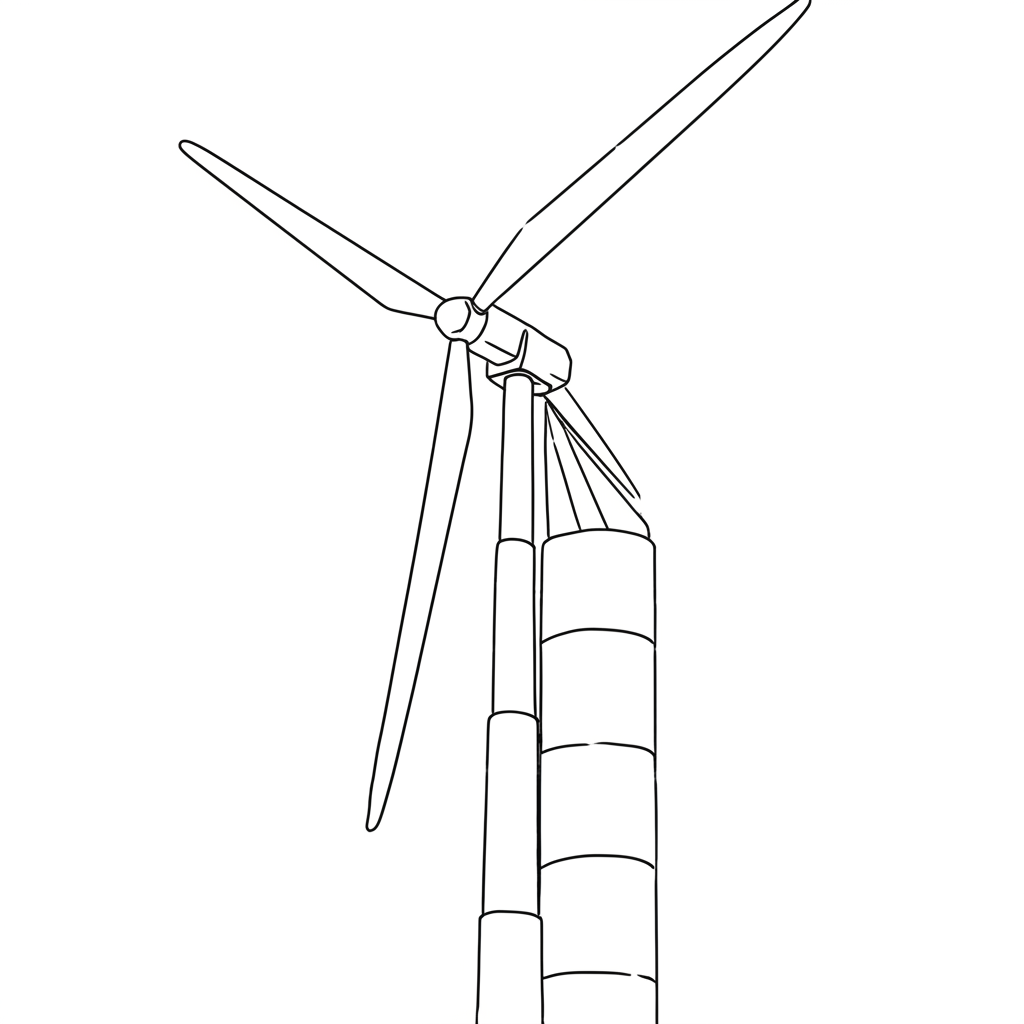 巨大風車の設置方法が想像を超えている!巨大な風力タービンがどのように建てられるのか、その裏側を動画で紹介。Redditの投稿から、驚きの設置風景を垣間見ることができる。
巨大風車の設置方法が想像を超えている!巨大な風力タービンがどのように建てられるのか、その裏側を動画で紹介。Redditの投稿から、驚きの設置風景を垣間見ることができる。
みんなの反応
えー、中に取り残される奴とかマジ勘弁だわ。
二番目に思ったのは、あたりめーだろ、風強いからそこに建ててんだよ!
マジで?もっと早くしろよ、詳細見れねーじゃんかよ!
10mmのソケットみたいに、100mmのソケットもよくなくなるのかな?
時々、タイヤ交換するときホイールのスタッドボルトの位置合わせるのすら苦労するわ。
あの油圧レンチ/トルク倍力装置、マジで美しいな。
あんなの建てるには、とんでもない玉が必要だな。
これはマジですごい。
でっかい玉だな。
精密な製造技術だな。
詳しい人に聞きたいんだけど、あれはベースのスタッドボルトの最終トルク締めにテンショナー使ってる?もしそうなら、ベース全体に均等なトルクをかけるために複数のテンショナーを同時に動かしてるの?それとも一つずつ?あと、中間のクランプボルトはただの油圧レンチ?もしそうならメーカーはどこ?
その動画、俺の好みからすると加速が足りないな。
思ってたよりデカい
あの変圧器、内側にあるのか。めっちゃ興味深いわ。
へー、グリーンエネルギーってめっちゃ仕事を生み出すんだな。
こんなに早く組み立てられるなんて知らなかった。すごいな。
完成してボルトが1本余ったらどうなるんだろうな。
全部高そう(小学生並みの感想)
それってIKEAのフラットパックみたいなもんじゃん。
「みんな、発電機のプラグ挿すの忘れてた!」
あれ、クロス締めじゃない気がするんだけど
あれが風車の組み立て方か。
どうやってんだろう?いや、クールだけど、風力タービンを立てるって想像してた通りだわ。
こういうのって、巨大物恐怖症を刺激されるんだよな。
最初に思ったのは。こんなに頑張っても、海の一滴にしかならないんだな。
あのe-radとかトルクガンで締め付ける音がどれだけうるさいかがないな。
あの作業員たち、マジで金玉デカすぎ。
IKEAの家具もこれくらい完璧に位置が合えばいいのに。
部品を吊り下げて、スタッドボルトが曲がってて位置が合わないのを見た時の絶望感ときたらもう…。
なぜか15メートルくらいのトルクレンチが出てくると思ってた。
あのボルトのトルクってどれくらいなんだろう。
**90年代初頭のバルカン戦争中、ボスニア・ヘルツェゴビナで何百ものDIY「ミニ」風力タービンに出くわしたことがある。廃品回収された家電製品のモーター(発電機として)と1つまたは複数の12ボルトの自動車用バッテリーに接続され、タービンは通常、煙突または建物に取り付けられたポールに取り付けられていた。同様のコンセプトが、全国の村々で水力タービン(水車)装置を使用して小川や川沿いで利用されていた。**
なんでボルトを下から上に設置して、ナットを上にするんだろう?俺の直感だと、上からボルトを落として、下からナットを持ち上げてネジを締める方がいいと思うんだけど。それに、もしナットが緩んだ場合でも、少なくともボルトの軸がせん断運動に対する一種のガイドピンとして機能するかもしれないし。




コメント