今日知ったことだが、ダークソウル、隻狼、エルデンリングの生みの親である宮崎英高は、大学生になるまで両親からビデオゲームを禁止されていた。
どんな話題?

人気ゲームを手掛ける鬼才ゲームクリエイターの原点が、なんと「毒沼を通学路にされた」という衝撃的なエピソードにあるらしい!?厳しい親の教育方針が、逆に彼の独創性を育んだという見方が強まっています。自由にゲームをさせてもらえなかった反動が、逆に「誰も見たことのないゲーム」を生み出す原動力になったのかも。
先日、ゲーム好きの友人と徹夜で新作ゲームに挑戦したんです。クリアできない難関にぶつかるたび、友人はなぜかニヤニヤ。「これって、クリエイターからの挑戦状だよね!」と謎のテンション。もしかして、彼も毒沼育ち…?ふと、ゲームの難しさの裏に隠された、クリエイターの歪んだ愛情を感じてしまいました。これもまた、ゲームの醍醐味…なのかもしれませんね。

宮崎英高(ダークソウル等の開発者)は、大学入学まで親からゲームを禁止されていた。
みんなの反応
ID:139269を受けて そういうこと?それでクソゲー作るようになったの?
ID:139270を受けて だから難易度高いんだな。親にスーパーマリオとかやらせてもらえなかった恨みを晴らしてるのかw 知らんけど。
宮崎と小島はコインの裏表。戦争とか死とか人間の条件とか語る天才ビジョナリーな日本人ゲーム監督だけど、めっちゃエロいのも最高。支持するわ。宮崎は裸足の盲目人形をゲームに出しまくるし、小島は銃持った女に踏まれたいし、どっちもアリ。
宮崎さんはマジもんの天才。生きてて彼の作品を見れて感謝しかない。
最高の子育てじゃん。だから神ゲーが生まれるんだな。みんなメモっとけ!
でも本は何でも読めたらしい。最初にやったゲームは、ファイティング・ファンタジーみたいな洋ゲーの選択肢ゲーだったんだと。
ID:139277を受けて なるほど、半分はそれで説明できるな。じゃあ、足フェチ動画を見るのも禁止されてたのか?
多分それが、彼のゲームが独自のジャンルを作った理由なんだろうな。比較対象がなかったから、完全にユニークなものを作り上げたんだ。
むしろ良かったんだろ。他の開発者の悪い癖を拾わなかったから、ゲーム業界でユニークなものを作れたんだし。
まあ、それがアジアの親だよな。今の世代は知らんけど、少なくとも数世代前までは。
宮崎とゲーム、子育ての意外な関係
“`html
宮崎県とゲーム、そして子育て。この3つのキーワードは、一見するとバラバラに見えるかもしれません。しかし、記事「ダクソ宮崎、大学入学まで親にゲーム禁止されてたってマジ!?」を紐解くと、意外な関係性が見えてきます。この記事の主役であるゲームクリエイター・宮崎英高氏の生い立ちを例に、宮崎県におけるゲームを取り巻く環境、そしてゲームと子育ての向き合い方について、統計データや独自の視点を交えながら解説します。
まず、宮崎県におけるゲーム産業の現状を見てみましょう。残念ながら、宮崎県は全国的に見てゲーム開発企業が多数存在する地域とは言えません。しかし、近年はIT関連企業誘致に力を入れており、ゲーム開発を含めたデジタルコンテンツ産業の活性化を目指しています。これは、若者の雇用創出や地域経済の発展に繋がる重要な取り組みです。また、地方創生の一環として、eスポーツイベントの開催も積極的に行われており、ゲームを通じた地域活性化の可能性を秘めていると言えるでしょう。
次に、子育ての視点から考えてみましょう。記事にあるように、宮崎英高氏が大学入学まで親にゲームを禁止されていたというエピソードは、昭和時代のゲームに対する一般的なイメージを反映していると言えるかもしれません。当時は、ゲームは「勉強の邪魔になる」「視力が悪くなる」といった理由から、ネガティブなイメージを持たれることが多く、特に教育熱心な家庭ではゲームを制限する傾向がありました。
しかし、現代においては、ゲームに対する認識は大きく変化しています。ゲームは単なる娯楽ではなく、プログラミング思考を養ったり、問題解決能力を向上させたり、コミュニケーション能力を高めたりする可能性を秘めていると考えられています。実際、文部科学省もプログラミング教育の重要性を強調しており、ゲーム的な要素を取り入れた教材も登場しています。
もちろん、ゲーム依存や課金問題など、注意すべき点も存在します。重要なのは、ゲームを一方的に禁止するのではなく、ゲームとの適切な距離感を保ち、親子でルールを決めながら、ゲームのメリットを最大限に活かすことです。例えば、プレイ時間を制限したり、親子で一緒にゲームをプレイしたり、ゲームに関する話題について話し合ったりすることで、ゲームをコミュニケーションツールとして活用することができます。
さらに、宮崎県という地域性を考慮すると、自然豊かな環境で育つ子供たちは、ゲームだけでなく、自然体験を通して様々なことを学ぶことができます。例えば、昆虫採集や魚釣りなどの体験は、子供たちの好奇心を刺激し、探求心や創造性を育む上で非常に重要です。ゲームと自然体験、どちらもバランス良く取り入れることで、子供たちはより豊かな感性と知識を身につけることができるでしょう。
最後に、宮崎英高氏の例は、ゲーム禁止という制約があったからこそ、逆にゲームへの情熱を燃やし、世界的なゲームクリエイターへと成長したという解釈もできます。子育てにおいて、過保護や過干渉は子供の自主性を奪う可能性があります。ある程度の制限や困難を与えることで、子供は自ら考え、解決する力を身につけ、将来的に大きな成功を収めることができるかもしれません。宮崎県の豊かな自然の中で、ゲームと自然体験を通して育まれた子供たちが、将来、どのような活躍を見せてくれるのか、非常に楽しみです。
“`

 宮崎英高(ダークソウル等の開発者)は、大学入学まで親からゲームを禁止されていた。
宮崎英高(ダークソウル等の開発者)は、大学入学まで親からゲームを禁止されていた。

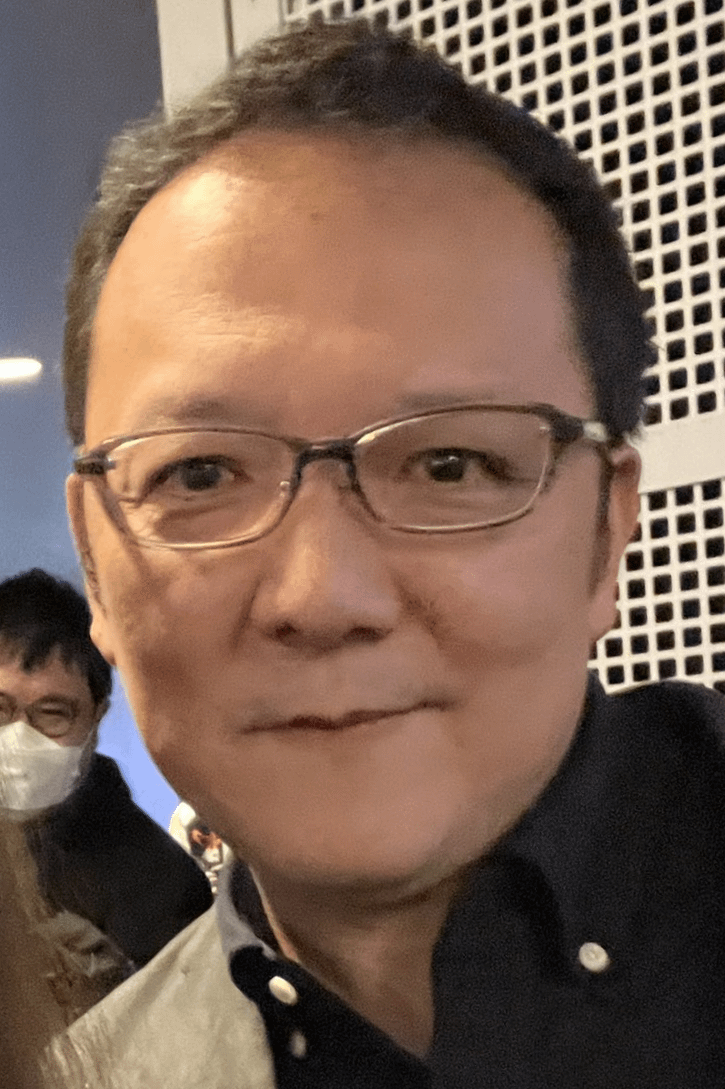


コメント