Man feeds a deer… Next day it brings the entire herd!
byu/HamZam_I_Am ininterestingasfuck
どんな話題?

ある男性が、数日の間に野生の鹿たちと急接近。餌を与えたところ、あっという間に大群が押し寄せるようになったという話題がSNSで拡散され、「まるでディズニープリンセスみたい!」と話題沸騰中。
しかし、動画を見た人たちからは「これは野生の鹿じゃない」「飼育されている鹿だ」という声も。多くの人が、野生動物への安易な餌付けに警鐘を鳴らしています。野生動物は感染症のリスクもあり、生態系への影響も懸念されるため、むやみな接触は避けるべきでしょう。
実は私も、田舎に帰省した際、畑の野菜を荒らすイノシシに遭遇。最初は怖かったのですが、毎日顔を合わせるうちに、なんだかトロンとした目が可愛く見えてきて…。でも、近所のおじいちゃんに「甘やかすと大変なことになるぞ!」と𠮟られ、我に返った経験があります。野生動物との距離感、本当に難しいですね。
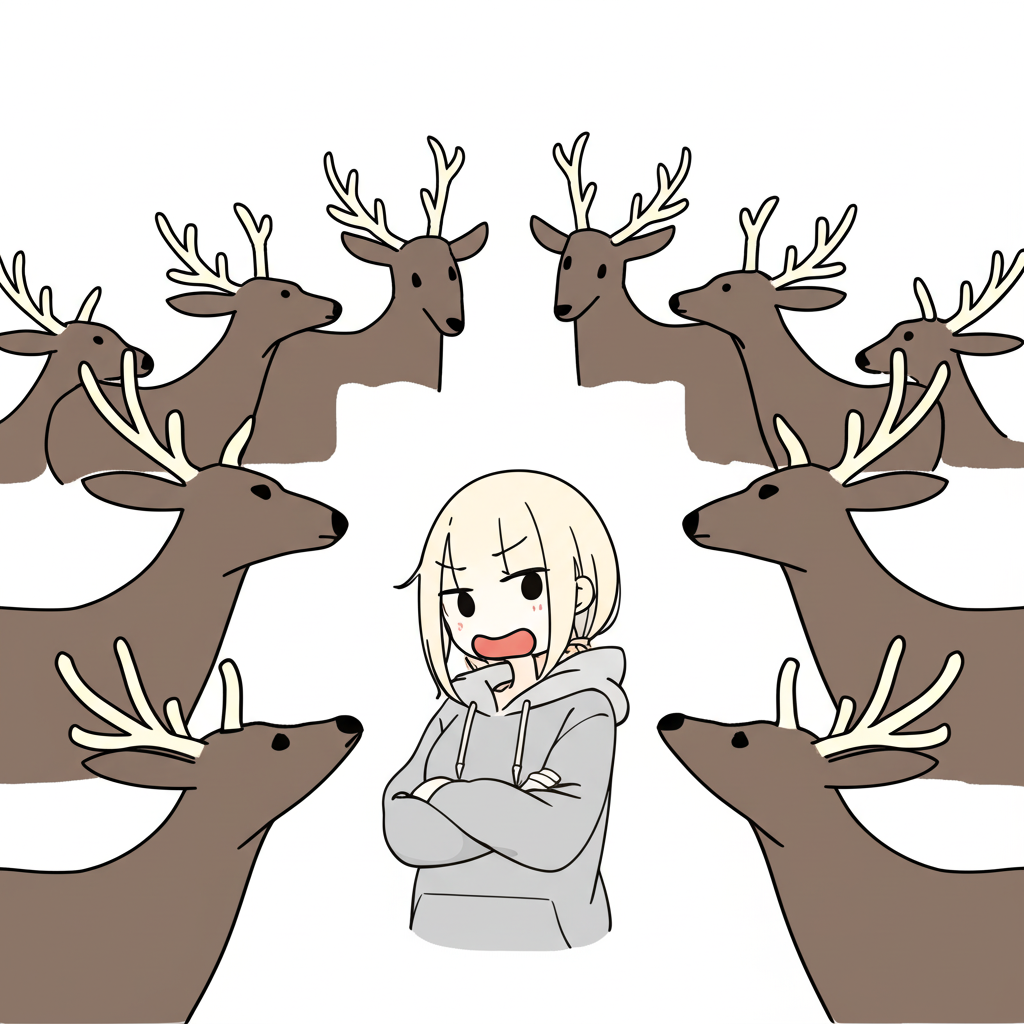 ある人が鹿に餌をあげた翌日、鹿が仲間を大勢引き連れて現れた様子を写した画像とRedditの投稿が話題に。「餌をあげたら大群で来た!」という驚きと面白さを伝えている。
ある人が鹿に餌をあげた翌日、鹿が仲間を大勢引き連れて現れた様子を写した画像とRedditの投稿が話題に。「餌をあげたら大群で来た!」という驚きと面白さを伝えている。
みんなの反応
もう仲間入りしとるやんけwww
ディズニーのプリンセスやんけ!
なんか覚えがあるな…コレ、「牧場のシカ」だろ。野生のシカの群れが、こんな短期間で人間に慣れるわけねーし。動画自体は面白いけどな。
1日目:子鹿に、古くなったグラノーラを手のひら一杯に与える。
え、一回餌やっただけでこうなるの?
野生動物に餌付けするなって、あれほど言われてるのに…
だから野生動物に餌付けしちゃダメなんだってば。
めっちゃ可愛い😊
いやいや、絶対に野生のシカじゃないって。あんな風に近づいても逃げないとかありえない。避けてるだけだし。
これを見てると、誰かが助けた怪我した鳥の動画を思い出すな。次の日、鳥の仲間たちがみんな来たっていうやつ。
プリオン病をジョークにしてんのか、オイ!?
野生動物をペット扱いするなよ。自然は自然のままにしておけ。
だから野生動物に餌付けしちゃダメなんだって。
あれは野生のシカじゃないわー(笑)
可愛すぎる!
シカシカ!
タイトル詐欺だろ。こいつ、もう何年も餌付けしてるんだろ。
まーた白雪姫ごっこかよwww
ダニ
可哀想に。野生でも餌があるといいね。
最初に餌があるって他のシカをどうやって説得したんだろう? 話せないのに。
動物に餌を与えないで!
少数意見:野生動物の幸せを願うなら、餌を与えないこと。
これが、慢性消耗病を広める原因なんだよな。
これが2日間で起こったって? ウソだ!
野生動物に餌を与えるな。
これが野生動物に餌をあげちゃいけない理由。
どれだけのシカのフンが残されるんだろうか。
これ、シカ牧場で撮影されたものだと思うんだけど。
「なぁ、知り合いがいるんだ…」
シカってマジで口が軽いよな。せっかく良い感じだったのに、自分だけ楽しめば良かったんだよ! 図々しさの極みだわ。本当に100匹分の餌があると思ってんのかよ。 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️




コメント